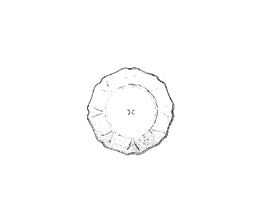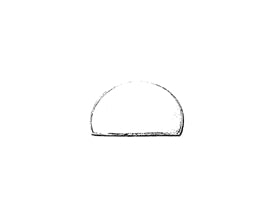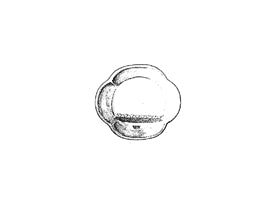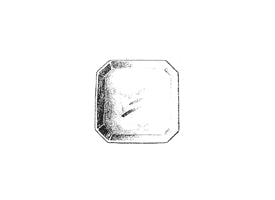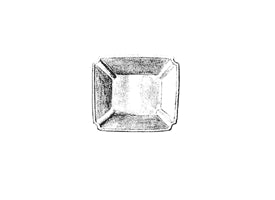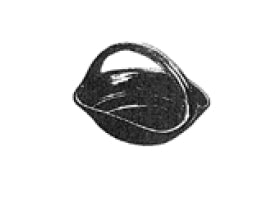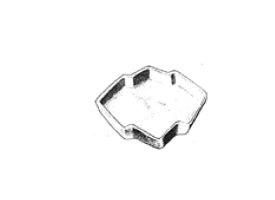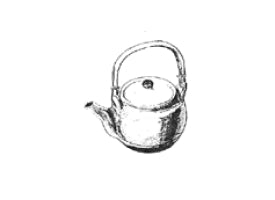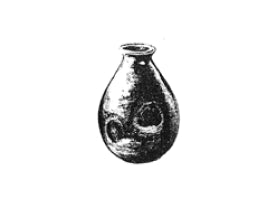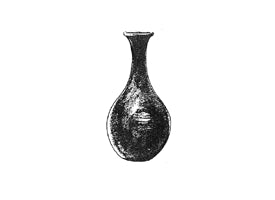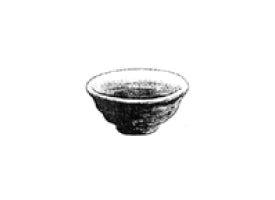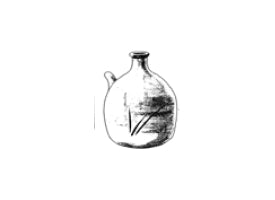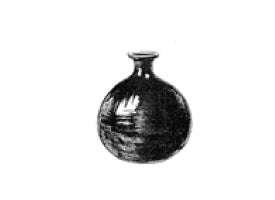やきものの扱い方や器の名称、かたちについてご紹介します。
Pottery & Porcelain 「陶器」と「磁器」
やきものは大きく分けて「陶器」と「磁器」にわかれます。
違いは材料。
一般的に陶器は土もの、磁器は石ものと呼ばれます。
土ものは主に粘土を原料とし、石ものは陶石と呼ばれる石の粉に粘土を混ぜたものが原料です。
材料が違うため、特徴が異なり、取り扱い方にも違いが現れます。
| 陶器 | 磁器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吸水性 | 有 | 十分乾燥してから収納する(しみこんだ水分がカビの原因になります) |
無 | 水気をふき取ったあとすぐに収納してもOK |
| 保温性 | 有 | 熱しにくく冷めにくい |
無 | 熱しやすく冷めやすい |
| 耐衝撃 | 弱 | 磁器と比べて弱い |
強 | 陶器と比べて強い |
陶器(土もの)の扱い方
「陶器(土もの)」は吸水性があるため、一手間かけてあげることで気持ちよく使えます。
● 使う前の一手間
30分水に浸してあらかじめ水分を含ませましょう。汁や油を吸収しにくくなります。
● 使った後の一手間
出来るだけ早く汚れを落とし、よく乾燥させてから収納しましょう。磁器(石もの)の扱い方
磁器(石もの)」は吸水性もなく、比較的衝撃にも強いため、特に注意することはありません。
※金・銀・絵付けのあるやきものは、電子レンジやオーブンにはお使いいただけません。
Design 器のかたち
ろくろでの成形、型や粘土板による成形など陶磁器の形は様々あります。
ここでは皿や鉢、向付、茶器、徳利、酒器などの伝統の「形」、「呼称」を見てみましょう。
皿
皿のサイズは一般に寸や尺で表します。
一般に30センチ前後(約一尺)以上の皿を大皿、12センチ(約五寸)以下は小皿、その間を中皿といいます。
現在では、円形や多角形を中心に自由な形のものも多く出てきています。
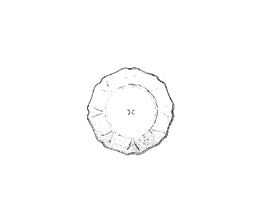
輪花
(りんか)
長皿・まな板皿
(ながさら・まないたさら)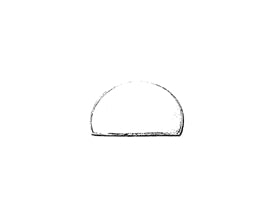
半月
(はんげつ)
木葉
(このは)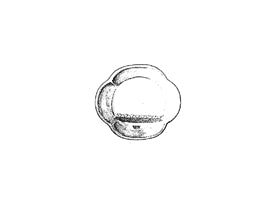
木瓜形
(もっこうがた)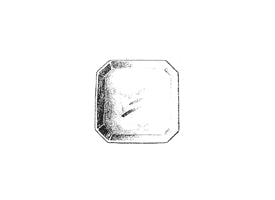
隅切り
(すみきり)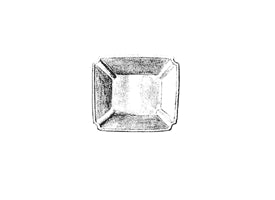
入隅額皿
(いりずみがくざら)
鉢・向付
少し深めの器を一般に鉢と呼んでいます。
向付は、小振りの鉢類を指しており、会席(懐石)料理で膳の奥(向こう側)につける料理をこう呼ぶことからきています。

片口
(かたくち)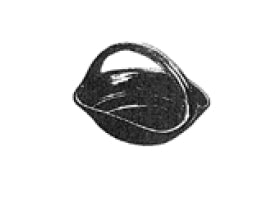
手付鉢
(てつきばち)
銅鑼鉢
(どらばち)
高台鉢
(こうだいばち)
編笠
(あみかさ)
菊鉢
(きくばち)
切落し
(きりおとし)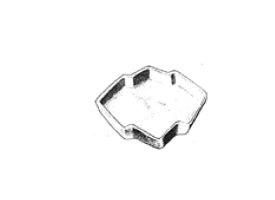
松皮菱
(まつかわびし)
蛤形
(はまぐりがた)
分銅
(ぶんどう)
扇形
(おうぎがた)
割山椒
(わりさんしょ)
舟形
(ふながた)
角違い
(かくちがい)
筒形
(つつがた)
柿形
(かきがた)
茶器
急須・土瓶・湯冷ましや湯こぼし、茶碗(湯呑み・汲出し・抹茶茶碗)などがあります。
急須も土瓶も昔は酒器として使われていました。
汲出しはもともと茶会の席で白湯(さゆ)を出すときに使われたもので、湯呑みが筒形が多いのに比べ、口に向かって開いた碗の形をしているものが多いです。

湯呑み
(ゆのみ)
汲出し
(くみだし)
急須
(きゅうす)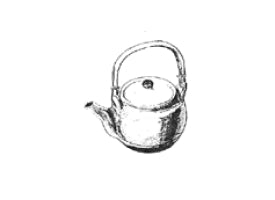
土瓶
(どびん)
煎茶器・急須・こぼし・茶碗
(せんちゃき、きゅうす、こぼし、ちゃわん)
徳利・酒器
酒を注ぐ容器としては、昔から徳利、片口鉢、また注ぎ口をつけたいろいろな形のものがあります。
酒を受ける器は、ぐい呑み、盃です。大振りのものをぐい呑みと呼んでいるようです。
よく使われる「猪口(ちょこ)」は、深めの小さな器の総称です。
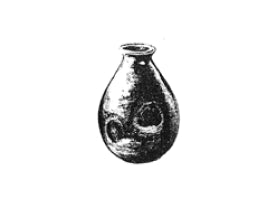
えくぼ徳利
(えくぼとっくり)
浮徳利
(うきとっくり)
らっきょう徳利
(らっきょうとっくり)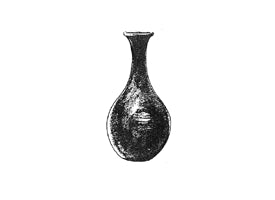
鶴首
(つるくび)
貧之徳利
(びんぼうとっくり)
傘徳利
(かさとっくり)
ろうそく徳利
(ろうそくとっくり)
瓢形
(ひさごかた)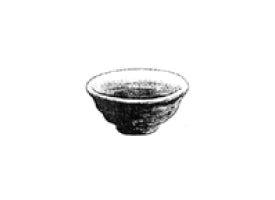
ぐい呑み(平)
(ぐいのみ)
ぐい呑み(立ち)
(ぐいのみ)
馬上杯
(ばじょうはい)
麦酒杯
(ばくしゅはい)
船徳利
(ふなとっくり)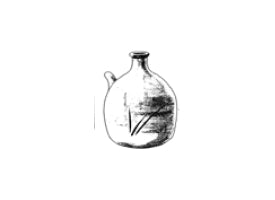
雲助徳利
(うんすけとっくり)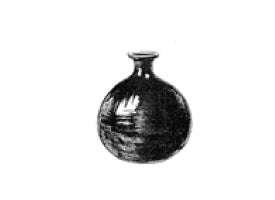
瓶子
(へいし)
からから

茶家
(ちょか)
銚子
(ちょうし)